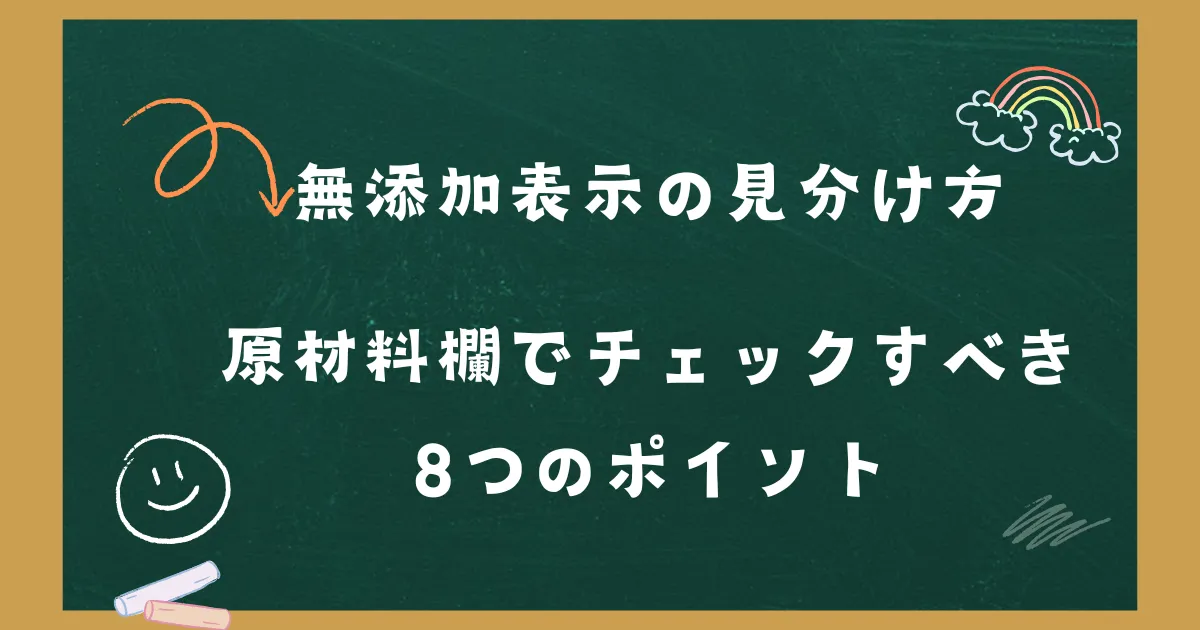※本記事はAmazonアソシエイトのリンクを含みます。
無添加表示を信じていいの? 原材料欄から「本当の中身」を見抜くポイント
この記事でわかること:
- なぜ“無添加”と書かれていても添加物が入っているのか?
- 原材料欄を読むための具体的な手順と8つのチェックポイント
- スマホ撮影を使った時短チェックのやり方まで解説!
原材料欄は「重量順」+「/スラッシュ以降」がカギ
まず「スラッシュ以降」に何が書かれているかを見れば、添加物が一目でわかります。
食品表示法では、食品中に占める重量が多い順に原材料を記載し、「/(スラッシュ)」以降に添加物をまとめて記載するルールがあります。
この場合、「膨脹剤」と「香料」が添加物です。まずスラッシュ位置を探し、その右側を確認しましょう。
チェックすべき成分
以下のような成分が含まれていたら“添加物入り”と判断しましょう。
- 保存料:ソルビン酸K、安息香酸Na(漬物・練り物・ジュースに多い)
- 着色料:赤40、青1、カラメル色素など(見た目強化目的)
- 香料:合成バニリンなど(風味補強・再現)
- 甘味料:アスパルテーム、スクラロース(カロリーオフ食品に頻出)
- 酸化防止剤:BHA、BHT、亜硫酸塩(油や色素の劣化防止)
- 植物油脂の種類:パーム油、硬化油(“ショートニング”と記載されることも)
- 遺伝子組換えやコーティング剤:大豆レシチン、パラフィンワックス等
グレーゾーン:天然由来でも賛否が分かれる添加物
「天然由来」だからといって安心とは限りません。製造工程で化学処理を伴うものもあります。
カラメル色素、トレハロース、酵母エキスなどは、一見“自然っぽい”ですが、添加物と同等に避けたいと考える人もいます。
完全排除は難しくても、使用量の少ない製品を選ぶ、または家庭で味の調節をするなど、現実的な判断が大切です。
実践テク:スマホで原材料欄を撮影→拡大
店舗でパッと判断したいときは、スマホで撮って確認するのが効率的です。
- ステップ①:商品を真上から撮影(反射・ブレ注意)
- ステップ②:拡大してスラッシュ以降の添加物を確認
- ステップ③:知らない成分はメモ → 買うか判断(慣れれば30秒)
画質は「高」、iPhoneなら拡大鏡、Androidならズームアプリもおすすめです。
迷ったときの優先順位
すべてを避けるのは難しい場合、以下のような順で優先してチェックすると効果的です。
- 第一優先:保存料・防腐剤を含まない
- 第二優先:着色料・香料が少ない
- 第三優先:人工甘味料が使われていない
“無添加”ラベルをうのみにしない
「無添加」と書かれていても、何が無添加かは明示されていないことが多いです。
例:「合成着色料・香料 無添加」と表示されていても、保存料や甘味料が入っていることもあります。
無添加のすぐ近くに注釈があるかどうかを必ず確認しましょう。

無添加派でも知っておきたい“おいしさとの折り合い”
完全無添加食品は、賞味期限が短い/価格が高いといった特徴もあります。
冷凍・真空・窒素充填など、物理的な保存技術を使った製品なら、添加物なしでも安全性が確保できます。
ライフスタイルと予算に合った「折り合い点」を見つけるのが現実的です。
安心できるメーカーの商品を選ぶ
無添加食品を選ぶ際は、「どの会社が作っているか?」という視点も大切です。
たとえば、ミートボールで有名な石井食品は、「無添加調理」を長年続けている信頼できるメーカーです。食の安全性を重視しており、原材料や製造工程も明確に公開されています。
石井食品の商品は、冷蔵惣菜・レトルト・おかずセットなど、日常使いにぴったりです。
今の時期、無添加の『おせち料理』も種類が豊富にあります。
当サイトでは、こういった安心できるメーカーの商品紹介記事を順次作成しています。
クリックすると、当サイトの別ページへ遷移します。
👉 安心できるメーカー『石井食品』の記事はこちら
👉 安心できるメーカー『ノースカラーズ』の記事はこちら
👉 安心できるメーカー『とらや』の記事はこちら
👉 安心できるストア『Amazonオーガニックフード(有機JAS食品)ストア』の記事はこちら
まとめ
- スラッシュ以降を見て、保存料・着色料・香料の有無をチェック
- 天然由来でも製造工程が複雑なら“グレー”と認識する
- スマホ撮影で時短判断。迷ったら保存料→香料→甘味料の順
- 「無添加」表示だけに頼らず、注釈と原材料欄で判断する